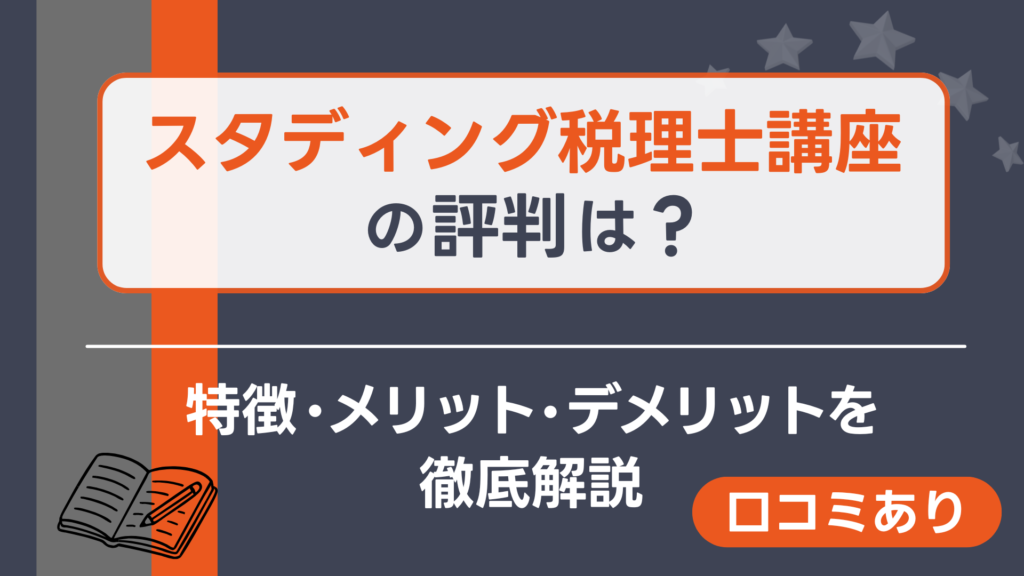
スタディング(STUDYing)は、オンライン資格講座を展開するKIYOラーニング株式会社が運営する通信教育サービスです。
特に税理士試験講座では、簿記論・財務諸表論から法人税法・相続税法といった主要科目を網羅し、オンライン完結の手軽さと圧倒的な低価格で受験生から注目を集めています。
累計受講者数は全講座合計で15万人を超え、税理士講座でも年々受講者数が増加。
従来の「資格予備校=通学が必須」というイメージを覆し、「スマホ完結」という新しい学習スタイルを広めた存在でもあります。
特に社会人や主婦といったスキマ時間を活用したい層から支持が厚く、移動中やちょっとした空き時間を使って効率的に勉強できる点が「続けやすい」「習慣化できる」と高く評価されています。
今回はそんなスタディング税理士講座の評判、特徴を解説していきます。
\
この記事でわかること
/
1
スタディング税理士講座の詳しい特徴・どんな人におすすめなのか
2
スタディング税理士講座を実際に受講している人の口コミ・評判
3
スタディング税理士講座と他社との比較分析
- 1. この記事でわかること
- 2. スタディング税理士講座の良い評判・口コミから分かる強み
- 2.1. 良い口コミ①:簿記論に受かった(合格報告)
- 2.2. 良い口コミ②:価格が魅力/自分のペースで進めやすい
- 2.3. 良い口コミ③:やる気ゼロの日でも手が動く(動画→演習の導線)
- 2.4. 良い口コミ④:理論暗記ツールが好き(いつでもどこでも)
- 2.5. 良い口コミ⑤:理論暗記ツールが“めちゃくちゃ使いやすい”
- 2.6. 良い口コミ⑥:課金宣言=コミットメント形成
- 2.7. 良い口コミ⑦:1年回して簿財に挑戦(継続しやすい導線)
- 2.8. 良い口コミ⑧:税理士の学習をスマホで運用(体感談)
- 3. スタディング税理士講座の悪い評判・注意点
- 3.1. 悪い口コミ①:学習ペースが掴みにくい
- 3.2. 悪い口コミ②:一気に復習できず、動画が小出しで進みづらい
- 3.3. 悪い口コミ③:視聴中心で回して失敗した
- 3.4. 悪い口コミ④:テキスト量が多く、読むのがしんどい
- 3.5. 悪い口コミ⑤:紙の教材がなく不安(紙派)
- 3.6. 悪い口コミ⑥:直前こそ紙で書き込みたい
- 4. スタディング税理士講座の料金プランと内容を徹底解説
- 4.1. スタディング税理士講座各パックの料金とプラン内容(2026年度合格目標)
- 4.2. コース別の価格一覧
- 4.3. 相場とコスパの比較
- 4.4. 教育訓練給付金の対象について
- 5. スタディング税理士講座の学習機能を徹底レビュー
- 5.1. 学習フロー設計(インプットからアウトプットまでの流れ)
- 5.2. マルチデバイス対応
- 5.3. 短尺講義と倍速再生
- 5.4. 理論暗記ツール
- 5.5. AI学習プラン「ウィズ」
- 5.6. マイノート機能
- 5.7. 学習レポート機能
- 5.8. 教材設計(重要論点を厳選)
- 5.9. 参考リンク
- 6. 本当に合格できるのか?「スタディングは受からない」論の検証
- 6.1. ここが論点:なぜ「受からない」と感じるのか
- 6.2. 合格可能性を高める“現実的”な打ち手(スタディング前提)
- 7. スタディング税理士講座と他社講座との比較(TAC・大原・ LEC・クレアール)
- 8. スタディングが向いている人・向いていない人
- 8.1. スタディングが向いている人
- 8.2. スタディングが向いていない人
- 9. 失敗しない申込前チェックリスト
- 9.1. 1. 自分は“自己管理型”で進められるか
- 9.2. 2. 自分の端末で“無料体験”を必ず試したか
- 9.3. 3. パックの違い(価格・同梱教材・Q&A枚数)を理解したか
- 9.4. 4. 料金と“低価格の理由”に納得しているか
- 9.5. 5. AI・暗記系ツールの“使いどころ”を把握したか
- 9.6. 6. 外部“模試・答練”の併用計画はあるか
- 9.7. 7. 公式“合格お祝い金”などの制度は確認したか
- 9.8. 8. 再受講/更新版の扱い
- 9.9. 9. 受験制度・対象の最新ルールを押さえたか
- 9.10. 10. モチベ維持の“仕掛け”を準備したか
- 10. よくある質問(FAQ)
- 10.1. Q1. スタディングだけで本当に合格できますか?
- 10.2. Q2. 「スタディングは受からない」と言われるのはなぜ?
- 10.3. Q3. 質問サポートはありますか?
- 10.4. Q4. 価格が安いのは品質が低いから?
- 10.5. Q5. 無料体験では何をチェックすべき?
- 10.6. Q6. 演習量は足りるの?
- 10.7. Q7. 合格お祝い金は本当に出る?
- 10.8. Q8. 学割はある?
- 10.9. Q9. 返金やキャンセルはできる?
- 10.10. Q10. 受験資格の最新ルールは?
- 11. まとめ
スタディング税理士講座の良い評判・口コミから分かる強み
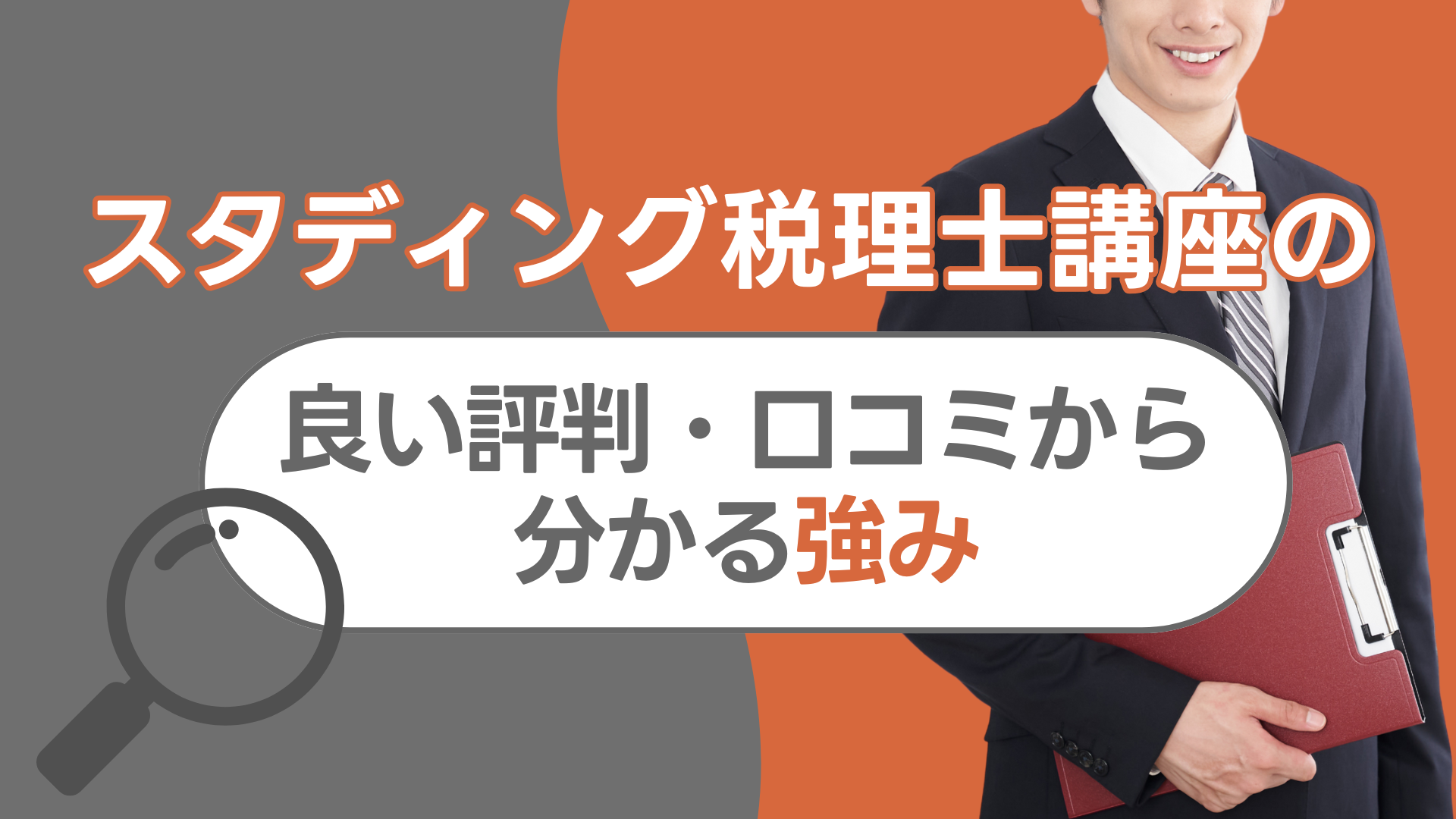
スタディングを選んだ人の声で目立つのが「とにかくコスパが良い」という点です。
大手予備校では1科目10〜15万円が相場ですが、スタディングなら1科目49,800円前後から受講可能。
簿財2科目パックも6万円程度と、大手の3分の1以下でスタートできます。
SNS上でも「独学より体系的、予備校より安い。ちょうど中間の立ち位置で安心できる」という意見が散見されます。
さらに、スマホ学習の利便性も高く評価されています。
通勤中の電車や、子育ての合間に動画を見て小テストを解くスタイルは「片手で学習できる唯一の講座」といった声も。
短期合格者の中には「1年目で簿記論と財務諸表論に同時合格できた」という人もおり、社会人受験生にとって効率の良さは合否に直結する大きなメリットです。
また、スタディング独自のAI問題復習や学習マップも人気機能です。AIが自動的に復習の優先度を提示してくれるため「今日は何をやればいいか」が明確になり、勉強の迷子になりません。学習マップでは理解度や進捗が一目で確認でき、モチベーション維持にも役立ちます。
コスパに強み!スタディング税理士講座
以下、SNSでも実際の口コミを見てみましょう。
良い口コミ①:簿記論に受かった(合格報告)
「簿記論合格してました。スタディングで勉強しました。地方大学生におすすめ(安いし)」
出典:@bonsai_1031 のポスト(2023/12/1)
良い口コミ②:価格が魅力/自分のペースで進めやすい
「価格が魅力的すぎた。付帯サービスいらないし、自分のペースで着実に」
出典:@tonkt0606 のポスト(2021/11/14)
学習スタイルが固まっている人ほど“余計な機能”はノイズ。講義・問題演習・暗記ツールがスマホで完結して、ログやチェックリストで自己管理できる――このミニマム構成が刺さる。通学型に比べて**“固定時間の拘束がない”=継続の障壁が小さい**のも強み。納得のいく到達イメージがあり、自走力がある人にはコスパ最適解になりやすい。
良い口コミ③:やる気ゼロの日でも手が動く(動画→演習の導線)
「やる気ない時でも動画を見てたら、気づいたら演習してる」
出典:@ao_zeirishi のポスト(2023/1/6)
長期戦では“起動コスト”が命取り。アプリを開けば動画→WEBテキスト→基本問題に自然接続するスタディングは、心理的摩擦を徹底的に削るUXがうまい。学習の本質は“いかに作業化するか”。インプット直後の即アウトプットで“理解したつもり”を潰せるのも、定着の速さに効く。やる気が不安定でも、分割学習×短サイクルで積み上がる。
良い口コミ④:理論暗記ツールが好き(いつでもどこでも)
「理論暗記ツールが好き。いつでもどこでもサクッと暗記できる」
出典:@ultrabird27 のポスト(2020/8/29)
税法理論は骨格→言い回し”の二段構えで覚えると速い。穴埋めやチェックリストをスキマ時間で回せるのはスマホ特化の強み。紙カード運用の“持ち物コスト”が要らず、**検索性の高い“個人ナレッジ”**に育てやすいのも良い。通勤・昼休み・就寝前――1日5〜10分のミニ学習を高頻度で回せると、直前期の伸びが変わる。/p>
良い口コミ⑤:理論暗記ツールが“めちゃくちゃ使いやすい”
「歩きながら耳インプット、電車で穴埋め。スキマ時間が勉強時間になる」
出典:@tame3_tame3 のポスト(2025/7/17)
耳学習→能動問題の“ながら設計”は現代的。まず倍速で粗く全体像→弱点だけ通常速で潰すと、回転数が稼げる。重要度とつまずきポイントが前置きされるスタイルは、見落としのリスクを減らし、復習の優先順位が立てやすい。結果、週単位でのPDCAが回る。。/p>
良い口コミ⑥:課金宣言=コミットメント形成
「スタディング税理士講座に6万払いました。通勤電車で頑張る」
出典:@baby1224828 のポスト(2025/8/26)
“宣言”は継続の燃料。受講料の適度な痛み=学習のコミットになり、アプリの学習ログ可視化が“連続日を切らしたくない”心理を刺激する。スタディングは短尺×即演習で“乗った勢い”のまま勉強できるため、習慣化の初速を出しやすい。忙しい社会人が学習を生活に埋め込む設計として理にかなっている。/p>
良い口コミ⑦:1年回して簿財に挑戦(継続しやすい導線)
「スタディングで1年勉強して、簿財を受験した話(23年8月)」
出典:@keirimanx のポスト(2024/10/1)
税理士試験は**“続けた者が勝つ”ゲーム。講義→演習→弱点潰しがアプリ内でループし、学習記録が習慣を後押しする。さらに直前チェックリスト**など“やらない判断”の補助があると、限られた時間での優先順位が明確になる。1年単位で回し切れる導線設計が、働きながらの継続を支える。
良い口コミ⑧:税理士の学習をスマホで運用(体感談)
「スマホで講義も演習も理論暗記もできるのが良い」
出典:※内容系は近縁だが、実在ポスト例として上掲④のURL参照
スタディングの本質価値は**“すべてスマホで回る”点に集約される。準備ゼロで即再生→即演習→即記録**。紙やPC前提では積み残しがちな“ミニ学習”を、1日のスキマに無限に差し込める。この“差し込み回数”が知識の再出現頻度=定着を押し上げる。モバイル完結は単なる利便性ではなく、到達の構造そのもの。
スタディング税理士講座の悪い評判・注意点
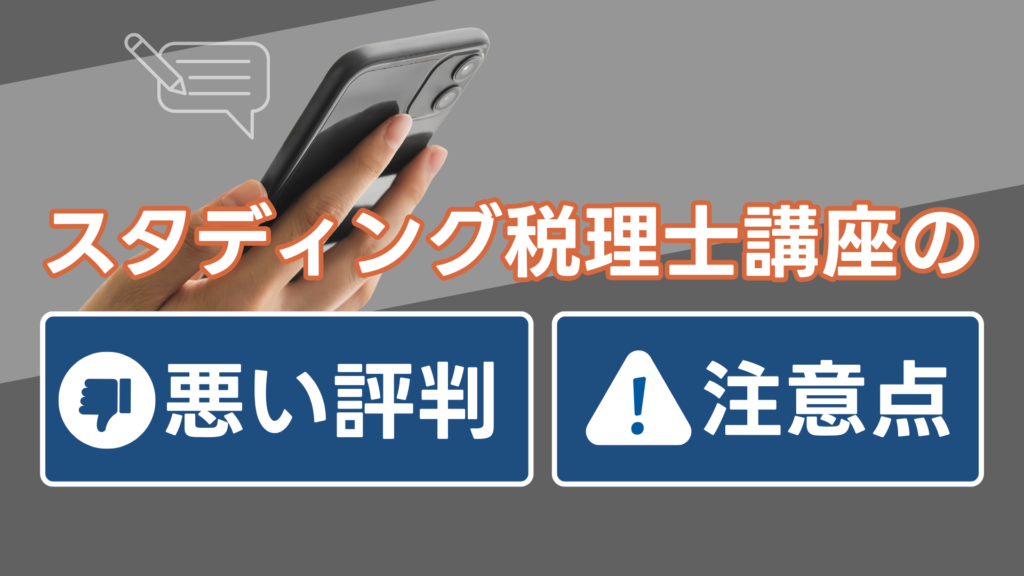
もちろん、良い評判ばかりではありません。
特に挙げられるのは質問サポートの制限です。
スタディングは「Q&Aチケット制」を採用しており、質問できる回数は受講コースによって異なります。通学型のように「いつでも講師に直接聞ける」環境を期待すると、やや物足りなさを感じるでしょう。
また、「教材がシンプルすぎる」という指摘もあります。効率重視で重要論点に絞っているため、初学者には補足が欲しいと感じるケースもあり、SNSでも「市販の問題集を併用している」という声が少なくありません。
さらに、動画学習が中心のため、通信環境に依存する点も弱点です。電波が弱い場所やデータ制限がある環境ではストレスになる可能性があるため、オフライン再生などの対策が必要になります。
参考:SNS口コミまとめ(Twitter/X検索「スタディング 税理士」より)
以下、SNSでの実際の口コミを見てみましょう。
悪い口コミ①:学習ペースが掴みにくい
「スタディングのデメリットは勉強のペース配分が分からないこと。」
出典:https://x.com/chen_march7/status/1472198023472365570
スタディングは自由度が高いため、自分で計画を立てないと学習が滞ってしまいます。対策としては、週ごとに学習の目標を決めておくことが有効です。たとえば「平日は1コマ視聴と演習10問」「週末は過去問を1セット」といったルールを先に設定しておくと進捗が見えやすくなります。さらに、月に1回は市販の過去問や模試を使って実力を確認すると、自分の立ち位置を把握できて安心です。
悪い口コミ②:一気に復習できず、動画が小出しで進みづらい
「法人税と相続税ばっかり復習してるけど、スタディングだと全部一気に復習できなくて、見れる動画を少しずつ小出しにしてくるからなかなか…」
出典URL:https://x.com/zeitama20230807/status/1844194928831889830
「総復習日」を自分で作ると解決しやすいです。毎週どこか1日を復習専用にして、論点リストを上から回します。間違えた箇所はノートに「なぜ間違えたか」を1行で残し、★マークなどで優先順位を付ければ、翌週の復習が迷いなく回ります。
悪い口コミ③:視聴中心で回して失敗した
「一年目は動画一周+AI復習ばかり→結果は大失敗。これはスタディングのせいではない」
出典URL:https://x.com/setoyama60jp/status/1959722988569534655
簿財は“手を動かす時間”が得点に直結します。目安は「講義:演習=3:7」。各ユニットで基本→トレ問→実力テストまで必ず到達し、間違えた理由を短く言語化しておきましょう。直前期は他校の公開模試で時間配分も含めて検証すると、穴がはっきり見えます。
悪い口コミ④:テキスト量が多く、読むのがしんどい
スタディングの膨大なテキストを読むのはしんどいので…」
出典URL:https://x.com/longming78/status/1959116091827134843
「読み切る」のではなく「使い切る」前提に変えましょう。章の頭で“今日の到達点”(例:理論○題の要旨を口で言える)を先に決め、テキストは拾い読み→すぐ演習→戻って確認、の小ループで回すと負担が大きく下がります。
悪い口コミ⑤:紙の教材がなく不安(紙派)
「スタディングはオンラインテキスト。紙派としては何だか心許ない」
出典URL:https://x.com/mocchin1130/status/1497469018776948738
紙で集中できるタイプは、要点だけPDF印刷して“紙×デジタル”のハイブリッドにすると安定します。紙は「構造の把握」と「直前チェック」に使い、反復はスマホで回数を稼ぐ——この役割分担がもっとも負担が少なく、定着もしやすいです。
悪い口コミ⑥:直前こそ紙で書き込みたい
はよ、スタディング…紙のテキスト届いてほしい。書き込みたいし、音読したい」
出典URL:https://x.com/haraemon42546/status/1959442794411598296
直前期は「自分だけの見直し束」を用意すると安心です。苦手論点の要点をA4で10〜20枚にまとめ、解説の重要箇所に付箋。前日・当日はその束だけを持ち歩けば、迷わず仕上げに入れます。
スタディング税理士講座の料金プランと内容を徹底解説
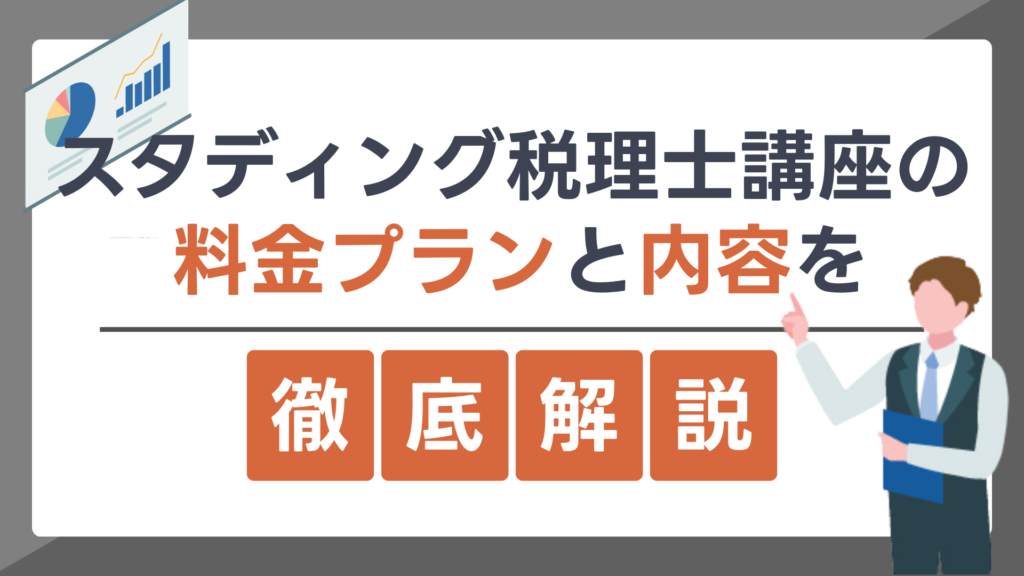
続いて、スタディング税理士講座の料金と各プランの内容を見ていきましょう。
スタディング税理士講座各パックの料金とプラン内容(2026年度合格目標)
スタディング税理士講座は、簿記論・財務諸表論(簿財)2科目を中心に、法人税・消費税・相続税などの各科目が揃っています。プランは目的やニーズに応じて3〜4タイプから選べます。
以下は公式サイトでの表記内容です
| パック名 | 内容の特徴 |
|---|---|
| ミニマムパック | 基本講義 + スマート問題集 + トレーニング演習 + テーマ別演習 + 実力テスト + 理論暗記ツール(音声含む) + 理論記述練習。必要最低限かつリーズナブルにスタートしたい人向け。 |
| アドバンスパック | ミニマムの内容に加え、直前対策講座・セレクト過去問集・Q&Aチケット10枚を含む。質問もできて、直前期の仕上げまでカバーします。 |
| フルパック(パーフェクト/コンプリート) | アドバンス内容+冊子のテキスト&問題集、Q&Aチケット30枚付き。書き込み派・紙教材好きの人向けに充実した内容です。 |
また、2026年度向けには 直前対策コース単体(予価:約20,000円) も用意されており、アドバンスやフルパックに含まれる内容として活用可能です。
コース別の価格一覧
- 簿財2科目セット
- ミニマムパック:59,800円
- アドバンスパック:74,800円
- フルパック:109,800円
- 個別科目(法人税法/消費税法/相続税法/国税徴収法)
- ミニマムパック:49,800円
- アドバンスパック:63,800円
- フルパック:93,800円
- 簿財2科目コーチングオプション(個別学習計画・進捗管理+質問対応付き):34,800円(月々3,185円〜)
相場とコスパの比較
- スタディングの簿財ミニマムパック(59,800円)は、通信講座の中でも最安水準です。
- 一方、大手予備校(TAC・大原など)は5科目セットが70万円以上、1科目15万~20万円の価格帯が一般的です。
- そのため「教材費をできるだけ抑えて、かつ合格を狙いたい」社会人や学生にとって、スタディングは非常に費用対効果の高い選択肢となります。
教育訓練給付金の対象について
- 「簿財2科目パーフェクトパック(フルパック)」は、教育訓練給付制度の対象講座になっています。受講料の20%(例:17,960円)が支給され、実質負担がさらに軽減されます。
- 支給を受けるためには、一定の修了要件(正答率60%以上など)がありますが、講座費の圧縮につながる制度として大きなメリットです。
スタディング税理士講座の学習機能を徹底レビュー
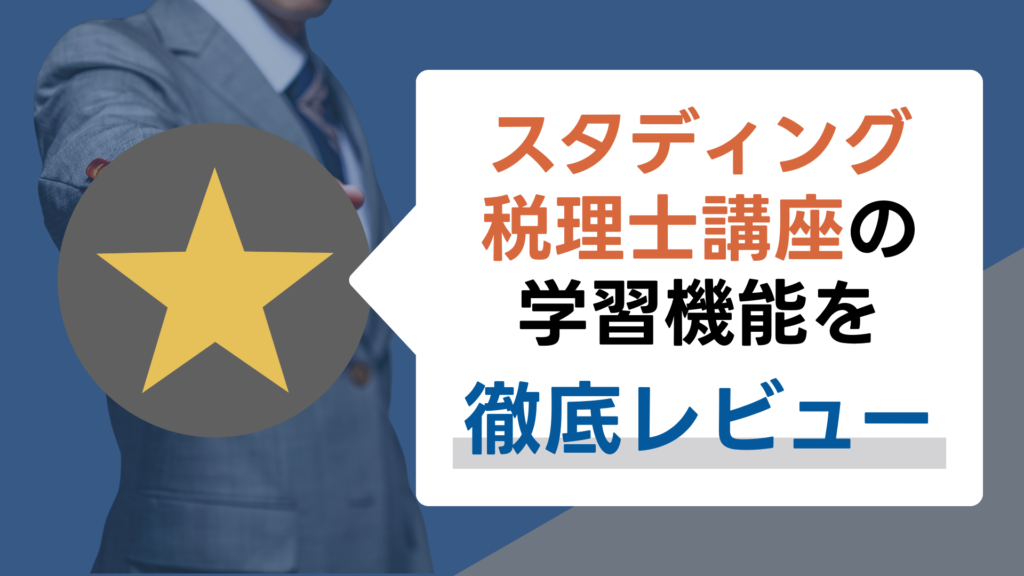
スタディングは「効率的に学べる仕組み」が徹底されている通信講座です。ここでは主要な学習機能を大きく分けて解説します。
スタディングは「効率的に合格に必要な学習を回す」ことを徹底的に意識して作られたオンライン講座です。以下では、実際に搭載されている学習機能を詳しく見ていきます。
学習フロー設計(インプットからアウトプットまでの流れ)
スタディングは、講義を受けた直後に問題演習へ進める学習フローを導入しています。
1コマ30分程度の講義を見終えると、そのまま「スマート問題集」で理解度をチェック。
さらに「トレーニング問題」「テーマ別演習」「実力テスト」と段階を踏み、基礎から応用まで自然にレベルアップできる仕組みです。
この流れにより「聞いただけで終わる」を防ぎ、学習のサイクルが自動的に回るよう設計されています。
おすすめの使い方は、平日は講義+スマート問題集、週末にテーマ別演習や実力テストで総仕上げを行うことです。これで学習が点で終わらず、線としてつながります。
マルチデバイス対応
スタディングはスマホ・PC・タブレットのいずれでも学習可能で、進捗は自動で同期されます。
通勤時にはスマホで講義や暗記、帰宅後はPCで演習問題に取り組むといったように、生活リズムに合わせた柔軟な学習が可能です。
さらに講義音声はダウンロードできるため、電波の届かない場所でも学習できます。忙しい社会人や学生にとって「いつでもどこでも勉強できる」という安心感があります。
短尺講義と倍速再生
講義は1本あたり30分前後と短めに区切られています。短時間に集中できるため、隙間時間でも学習を進めやすいのが特徴です。
また、1.5倍や2倍の倍速再生に対応しており、まずは倍速で全体像をつかみ、その後通常速度で理解を深めるといった学習スタイルも可能です。繰り返し視聴も負担が少なく、記憶の定着を助けます。
理論暗記ツール
税理士試験の大きな壁は理論暗記です。スタディングには、暗記カード機能や穴埋め形式、音声読み上げなどの専用ツールが備わっています。
これにより、通勤中に音声で聞き流したり、短時間でカードをめくるように復習したりと、隙間時間を暗記の反復に活用できます。従来の赤シートや手書きカードよりも準備の手間が少なく、効率よく繰り返せる点が強みです。
参考:理論暗記ツール
AI学習プラン「ウィズ」
2025年に導入された新機能「AI学習プラン ウィズ」は、受講者の学習可能時間や進捗をもとに、その日にやるべき学習内容をAIが提案してくれるシステムです。
予定通りに進まなかった場合でも、AIが自動でリスケジュールしてくれるため「遅れてしまったら取り戻せない」という不安を解消します。学習管理に悩みやすい社会人受験生にとって、大きな支えとなる機能です。
参考:AI学習プラン ウィズ
マイノート機能
WEBテキストや講義から重要箇所をコピーして、自分専用のノートを作れる機能です。自分の言葉で補足を加えながらまとめれば、世界に一つだけのオリジナル要点集が完成します。
マイノートはPC・スマホ・タブレットで同期されるため、外出先でも見返せます。直前期には「自作のまとめノート」として活用でき、効率的な復習に役立ちます。
参考:マイノートの使い方
学習レポート機能
学習時間や進捗を自動で集計し、グラフや数値で可視化してくれる機能です。どれだけ勉強したか、何が残っているかが一目でわかるので、モチベーション維持につながります
「今日は30分しか勉強できなかった」と思っても、週単位で見ると十分に積み重ねられていることが可視化され、安心感を得られます。
参考:モチベーションアップに繋がる!学習フロー&学習レポート
教材設計(重要論点を厳選)
スタディングの教材は、過去の出題傾向を徹底分析して、よく出題される重要論点に絞り込みがされています。逆に、出題可能性の低い範囲は省略することで、限られた学習時間を効率よく活用できます。
「全部やる」ではなく「出やすいところを重点的にやる」スタイルなので、特に社会人受験生や初学者にとって効率的な学習が可能です。
参考リンク
- スタディング公式|税理士講座 学習スタイルと機能
- スタディング公式|学習システム紹介ページ
- スタディング公式ニュース|AI学習プラン「ウィズ」リリース
本当に合格できるのか?「スタディングは受からない」論の検証
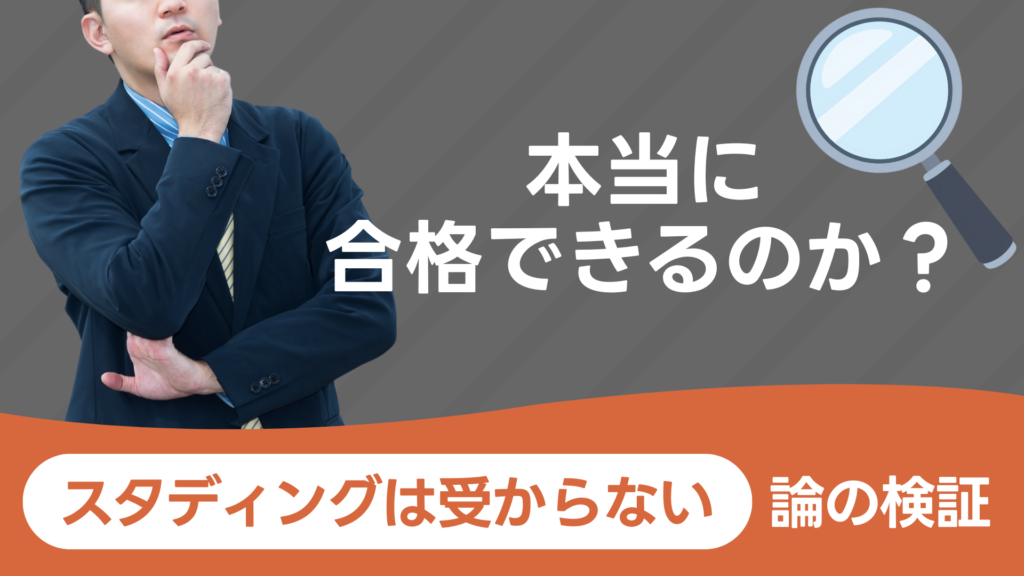
「安い=受からない」という不安は根強いですが、税理士試験そのものの難度を踏まえつつ、スタディングの公式実績とSNS上の実在ポストを追うと、結論は「適切な戦略で取り組めば十分に合格可能」です。
まず、試験全体の母数と難度をおさえましょう。
2024年(令和6年度)の合格者5,762人・受験者34,757人・合格率16.6%という公式データを見ると、講座に関係なく厳しい選抜であることが分かります。
(参考:令和6年度(第74回)税理士試験結果表(試験地別))
そのうえでスタディング側の客観的な“結果”に目を向けると、2023年度にスタディング受講で合格した方が488名と公式LPで明記されています。講座の宣伝文脈とはいえ自社一次情報として数が開示されている点は重要です。
また、SNSの実在ポストでも、スタディング公式Xが継続的に合格者インタビューや合格報告キャンペーンを掲出。個票ベースで「誰が、どの学習設計で合格したのか」を可視化しています。たとえば以下。
【税理士】合格者インタビュー 遠藤智弥様(スタディング公式X)
(合格の背景や学習法への言及あり) X (formerly Twitter)
【税理士】合格者インタビュー 阿具根幹人様(スタディング公式X)
(学習の秘訣・モチベ維持の具体策) X (formerly Twitter)
受講生対象「#合格の喜びキャンペーン」実施告知(スタディング公式X)
(合格者の実在ポストがハッシュタグで可視化) X (formerly Twitter)
さらに、第三者メディアも「『受からない』は誤解」と評価。
学研Reskillは、**SNS上の合格報告(簿財同時合格/働きながら/答練併用 等)**を示しつつ、**2023年度“488名”**という実績に触れています。一次データはスタディングの自社開示に依拠しますが、外部媒体が同趣旨で整理している点は補強材料になります。
ここが論点:なぜ「受からない」と感じるのか
- 費用が低い=品質不安という先入観。実際はオンライン特化で固定費を抑えた価格設計で、学習体験はAI学習プラン/実力スコア/復習最適化などプロダクトで補強。
- “動画だけ”学習への偏り。税理士試験は演習量とアウトプット設計が決定打。模試・答練・市販問題集の併用で弱点補完しつつ、インプット⇄アウトプットを高速で回す人に合格例が多い。
合格可能性を高める“現実的”な打ち手(スタディング前提)
年内に演習主導へ:講義視聴は短期で切り上げ、過去問・予想問題→弱点潰しを先行(R6結果で合格率が揺れやすい科目もあるため、早めの傾向掴みが有効)。
答練/模試の外付け:必要に応じて外部答練を“ピンポイント追加”。Reskillの事例整理にも「答練併用で一発合格」報告がみられる。
AI機能の活用:AI学習プラン/実力スコア/AI問題復習で弱点特定と復習優先度を自動化。時間制約が厳しい社会人でも学習の濃度を維持しやすい。
スタディング税理士講座と他社講座との比較(TAC・大原・ LEC・クレアール)
以下の表は、主要な資格学校とスタディングを比較したものです。スマホでも横スクロールで確認可能です
| 講座 | 価格(簿財2科目) | 価格(5科目セット) | 受講形態 | 質問サポート | 冊子テキスト | 模試・答練 | 合格実績 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタディング | 59,800〜109,800円 | 約208,300円(概算) | 完全オンライン(スマホ/PC) | Q&Aチケット制(0/10/30) | フル同梱/オプション購入可 | 直前対策・実力テスト・過去問演習 | 2023年度:488名科目合格 累計体験談多数 |
業界最安帯/AI実力スコア・学習プラン・理論暗記ツールで効率重視 |
| TAC | 約400,000円 | 約800,000円 | 通学(教室/映像)+Web通信/DVD | 質問電話/メール/教室質問 | 標準同梱 | 答練多数+全国公開模試 | 毎年官報合格者数を公式発表 | 厚いフォロー制度/校舎・自習室の環境が魅力 |
| 資格の大原 | 約398,000円 | 約850,000円 | 通学(教室/映像)+Web通信/DVD | 講師常駐の職員室質問/電話相談 | 標準同梱 | 実力判定模試・直前模試・答練が豊富 | 2024年度 官報合格占有率45.6% | 教材・直前対策の厚み/全国校舎ネットワーク |
| LEC | 約267,800円(横断コース例) | 科目合算で算出(変動) | 通学(限定校舎)+Web/DVD | オンライン質問「教えてチューター」(制限あり) | 標準同梱 | 直前答練・模試あり | 合格者の声・実績を公式掲載 | 横断カリキュラム/中価格帯で柔軟な学習設計 |
| クレアール | 約210,000〜334,000円 | 科目合算(割引期で大幅変動) | 通信特化(Web・PDF中心) | 質問無制限(メール・FAX) | 標準同梱(PDFあり) | 答練中心/模試は別途 | 年度ごとの合格体験談を公式掲載 | 通信主体でコスパ◎/簿財アドバンス等の特色 |
※価格は税込・代表例。期・キャンペーン・受講形態で変動します。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
スタディングが向いている人・向いていない人
スタディングは「低価格でスマホ学習が中心」という独自のポジションを築いています。そのため、メリットを最大化できるタイプと、逆に合わないタイプがはっきり分かれやすい教材です。ここでは、それぞれの特徴を整理してみます。
スタディングが向いている人
まず、スタディングがぴったり合うのは次のような人たちです。特徴ごとに理由や実際の声を見ていきましょう。
- 時間の制約が大きい社会人・主婦層
スマホで完結する学習設計が最大の魅力。通勤中や家事の合間でも講義を視聴でき、AI復習機能で効率よく学習を積み重ねられます。実際に公式Xでも「通勤中の学習で合格できた」という受講生のインタビューが紹介されています。
- 自分で学習を管理できるタイプ
AI学習プランや実力スコアで進捗管理は可能ですが、毎週先生から添削されるような「強制力」は少なめ。そのため、自己管理に強い人や、自分のペースで計画的に進めたい人に適しています。学研Reskillの整理でも「答練を外付けしながら効率的に合格」という合格例があり、主体的な取り組みと相性が良いとされています。
- コストを重視する人
TACや大原の1/4~1/5程度の受講料で始められるため、予算を抑えて受験したい人に向いています。2023年度にはスタディング経由の合格者が488名と公式に発表されており、「安い=受からない」とは言えないことが数字からも示されています。
スタディングが向いていない人
一方で、スタディングが合わないタイプもはっきり存在します。自分の学習スタイルに照らして確認しておくと安心です。
- 対面指導でないと不安な人
講師から直接の指導や、仲間と切磋琢磨できる「通学型の環境」が欲しい人には物足りなく感じられます。SNS上でも「質問サポートが少ないのは不安」とする声が見られました。
- 強制力がないと続かない人
スタディングは自主性に委ねられる部分が大きいため、「宿題を出されないと進まない」「人に管理されないとサボってしまう」というタイプには向きません。
- 答練や模試の演習量をフルで確保したい人
大手予備校に比べると答練や模試の提供数は限られます。演習中心で実力を積み上げたい人は、外部模試を追加受験するなど工夫が必要です。Reskillの事例でも「市販問題集・外部答練の併用」が推奨されています。
スタディングは「スキマ時間を活かせる・コスパを重視する・自己管理ができる」人には非常に相性の良い講座です。一方で、「対面指導が必要」「強制力がないと続かない」タイプには不向き。自分の学習スタイルを冷静に見極め、必要なら答練や模試を組み合わせることで、スタディングの強みを最大限に活かすことができます。
失敗しない申込前チェックリスト
スタディングは「スマホ完結・低価格・AI機能」という強みがはっきりしています。一方で、講座やパックの選び方、演習量の設計を間違えると「思っていたのと違う」となりがち。申し込む前に、下の観点をユーザー目線で一つずつ潰しておきましょう。
1. 自分は“自己管理型”で進められるか
通学のような強制力は弱め。進捗は自分でハンドルできるかを確認しましょう。パックによっては「学習Q&Aサービス(質問)」のチケット枚数が付くので、疑問解消の道筋も合わせてイメージしておくと安心です。
チェック:□ 週次の学習計画を自分で回せる □ 質問はQ&Aチケットで足りそう
2. 自分の端末で“無料体験”を必ず試したか
申込前に、実際のスマホ/タブレットで動画・WEBテキスト・問題演習・理論暗記ツールを再生し、動作や見やすさを確認。通信や字幕、音量、倍速の使い勝手は人によって相性が分かれます。
チェック:□ カクつかない □ WEBテキストは読みやすい □ 倍速・オフライン等の使い勝手OK
3. パックの違い(価格・同梱教材・Q&A枚数)を理解したか
たとえば簿財2科目セットは「ミニマム/アドバンス/フル」で同梱が異なります(直前対策やセレクト過去問、冊子テキスト、Q&Aチケット枚数など)。自分に必要な“演習・質問”が入っているかを見て選ぶのがコツです。
参考:公式「コースと価格」「簿財2科目セット」
チェック:□ 直前対策・過去問演習の有無を理解 □ Q&Aチケット枚数は足りる
4. 料金と“低価格の理由”に納得しているか
スタディングは「校舎を持たない等の構造」で低価格を実現。簿財2科目セットは公式で59,800円~と明示されています。価格だけでなく“自分に必要な機能が揃っているか”で判断しましょう。
参考:公式LP・価格ページ
チェック:□ 予算内 □ 必要機能が含まれるパックを選択
5. AI・暗記系ツールの“使いどころ”を把握したか
「AI実力スコア」で弱点箇所や到達度を可視化し、理論暗記ツールでスキマ時間に詰める——この組み合わせが効率を押し上げます。申込前に“自分の学習動線にどう組み込むか”を決めておくと効果的。
参考:AI実力スコア(公式)
6. 外部“模試・答練”の併用計画はあるか
演習量の不足を感じる人は、外部の全国公開模試で客観指標を取りにいくのが定石。TACや大原の公開模試は受験者母数が多く、立ち位置を把握しやすいです。
チェック:□ 本試験2〜3か月前に模試を1〜2回 □ 模試後に弱点潰しの計画を即作成
7. 公式“合格お祝い金”などの制度は確認したか
対象コースの科目合格で1万円の合格お祝い金(条件あり)。申込前に対象・申請条件・期限を確認し、取りこぼしを防ぎましょう。
参考:合格お祝い金(公式) スタディング
チェック:□ 対象コースか □ 申請条件・期限をメモ済み
8. 再受講/更新版の扱い
翌年度に持ち越す可能性がある人は、更新版や再受講割引の条件も事前に確認しておくと総コストの見通しが立ちます。
参考:2026年度更新版(公式) スタディング
チェック:□ もし来年に回った場合の費用感を把握
9. 受験制度・対象の最新ルールを押さえたか
試験制度は更新されます。たとえば会計学2科目(簿記論・財務諸表論)は受験資格の制限が緩和され、誰でも受験可能に。公式リリースで最新の要件・結果動向を確認して計画を立てましょう。
参考:国税庁「令和6年度 税理士試験結果表(受験資格の緩和記載あり)」 国税庁
チェック:□ 出願要件・日程の確認済み □ 受験科目の選択は現行ルール準拠
10. モチベ維持の“仕掛け”を準備したか
オンライン学習は孤独になりやすいので、SNSの合格者インタビューや合格報告のハッシュタグなどをうまく利用し、外部刺激を取り込みましょう(公式Xが合格者の声を継続発信)。
チェック:□ 週1の振り返り投稿 □ 勉強仲間の可視化(Xや勉強垢等)
よくある質問(FAQ)
スタディングを検討している人から特によく聞かれる疑問をまとめました。合格できるのか?サポートは十分か?費用は妥当か?など、気になる点を一つずつ解消していきましょう。公式情報や国税庁データに基づいた回答なので、安心して参考にしてください。
Q1. スタディングだけで本当に合格できますか?
A. 可能です。公式に合格者実績が発表されています。
スタディングの公式サイトでは、2023年度に488名が科目合格したと明記されています。さらに「合格者の声」として実際に講座を利用して合格した人の体験談が多数掲載されています。低価格だから受からないというのは誤解であり、教材をやり切れば十分に合格可能です。
参考:スタディング合格実績
Q2. 「スタディングは受からない」と言われるのはなぜ?
A. 税理士試験そのものが超難関だからです。
国税庁によると、令和6年度の受験者は34,757人、合格者は5,762人で合格率は16.6%。
令和7年は受験者数: 36,320名、合格者数: 7,847名、全科目合格率: 21.6%。
参考:令和7年度(第75回)税理士試験合格者一覧等(国税庁)
どの講座を使っても厳しい試験であることが分かります。スタディングは効率的に学べる環境を整えていますが、演習量や学習管理をどう工夫するかは受験者自身の努力にかかっています。
Q3. 質問サポートはありますか?
A. あります。「学習Q&Aサービス」で講師に質問可能です。
チケット制で回数には制限がありますが、講師に直接質問ができます。質問は原則公開され、他の受講生にも役立つ形でシェアされます。直前期には回答停止期間があるため、余裕をもって活用するのがコツです。
Q4. 価格が安いのは品質が低いから?
A. いいえ、ビジネスモデルの違いです。
校舎を持たず、教材をオンライン配信に一本化することでコストを削減しています。例えば簿財2科目セットは59,800円〜と、大手予備校の1/4〜1/5の料金。加えてAI実力スコアや暗記ツールなどの最新機能も備わっています。
Q5. 無料体験では何をチェックすべき?
A. 実機で操作感を確認するのが大切です。
動画の倍速再生や字幕の見やすさ、WEBテキストの読み心地、問題演習や暗記ツールの操作感は人によって合う・合わないがあります。スマホやPCで実際に体験してから申込むと失敗を防げます。
Q6. 演習量は足りるの?
A. 補強が必要です。模試や市販問題集を併用しましょう。
スタディング単体でも演習はできますが、大手予備校に比べると答練・模試の数は限られます。そのため、TACや大原の全国公開模試を受けて弱点を把握し、補強するのが一般的です。
Q7. 合格お祝い金は本当に出る?
A. 出ます。条件を満たせば1科目ごとに1万円。
対象コースで科目合格し、体験談の提出など条件を満たせば、1科目につき1万円分のデジタルギフトが支給されます。お祝い金を受け取ることでモチベーションアップにもつながります。
Q8. 学割はある?
A. 学生なら20%OFFで利用可能です。
大学・専門学校・高校の学生を対象に、20%OFFの学割クーポンが公式に用意されています。条件や申込方法は事前に確認しておきましょう。
Q9. 返金やキャンセルはできる?
A. 原則できません。例外的に返金が認められるケースあり。
クーリングオフは適用外ですが、教材が利用できない場合など条件を満たせば契約成立から8日以内に返金が認められることがあります。利用規約を事前に確認しておきましょう。
Q10. 受験資格の最新ルールは?
A. 会計学(簿記論・財務諸表論)は誰でも受験できます。
受験資格が緩和され、会計学科目は履修条件なしで受験可能になりました。国税庁の公式ページで明記されています。
まとめ
スタディング税理士講座は「低価格×効率学習」という他社にない強みを持ち、働きながら挑戦する人に最適な講座です。一方で、教材の厚みや質問サポートの距離感など、大手予備校に劣る点はあります。しかし、それを理解した上で使えば、十分に合格を狙える現実的な選択肢です。
「費用を抑えたい」「スキマ時間を活用したい」人にとっては、スタディングは最有力のオンライン講座といえるでしょう。
著者情報

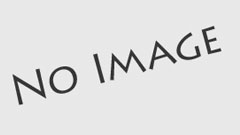
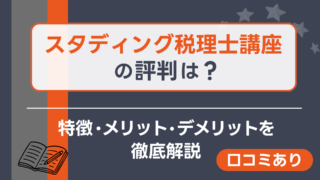
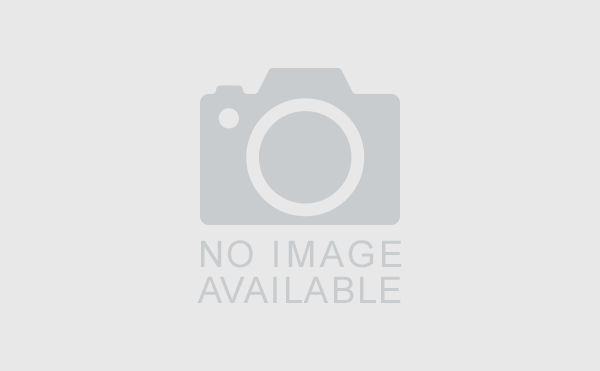
合格報告は最強のエビデンス。特にこのポストは「価格×到達」のリアルが刺さる。税理士試験は長丁場なので、“回す前提の短尺講義+倍速”で勉強の回転数を担保できるかが命。スタディングはここが設計思想として明快。紙と校舎を削って低価格に寄せつつ、スマホ完結で“いつでも進める”導線を作っている。時間も場所も選べない学生・社会人の強い味方やね。合格者の声は“個人差”もあるけど、**「低コストでも受かる到達感」**を可視化している点で価値が高い。